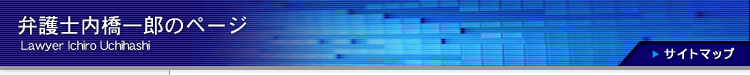|
|
 |
 |
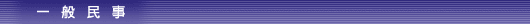 |
 |
| 一般民事 |
 |
 |
交通事故、売買、借地・借家、金銭貸借、保証などのさまざまな一般民事に関する法的紛争の法律相談、調停申し立て、訴訟などを担当します。 |
|
 |
| 交通事故Q&A |
 |
 |
Q1 |
休業損害
交通事故のために1ヶ月入院し、その後2ヶ月通院し、その間、会社を「休業」しました。どこまで補償してもらえるのでしょうか。 |
 |
 |
A1 |
交通事故によってけがをして入通院した場合の損害賠償としては、①「治療費」、②「付添看護費」、③「入院雑費」、④「通院交通費」、⑤「休業損害」、⑥「入通院慰謝料」の請求が可能です。
裁判基準では、入院で付添看護が必要な場合の「付添看護費」は1日6000円程度、入院雑費は1日1300円程度が認められています。
「休業損害」は受傷のために休業により現実に喪失した収入額です。算定のための基礎収入は事故直前の実収入額を用います。収入がない場合には休業損害は認められません。
「入通院慰謝料」については、重傷度(通常、重傷)に応じて、1ヶ月の入院でいくら、通院でいくらと目安となる裁判基準があります。大阪弁護士会の発行している「交通事故損害賠償額算定のしおり」によれば、平成14年の事故であれば、1ヶ月入院は48万円が目安とされています(この金額は自賠責保険の基準とは異なります)。 |
 |
 |
Q2 |
後遺症
交通事故で「後遺症」が残りました。保険会社の人の話だと、私の後遺症の程度は自賠責保険後遺障害等級9級であるとのことです。後遺症の損害賠償額はどのようにして決まるのでしょうか。 |
 |
 |
A2 |
後遺症が残った場合には「逸失利益」と「後遺症慰謝料」が問題になります。
「逸失利益」とは、後遺症がなければ働いて得られたであろう利益をいいます。
逸失利益は事故直前の収入を基礎として、後遺症の程度によって定められた労働能力の喪失率を乗じ、これに労働能力喪失期間に対応した一定の係数を乗じて算定します。
例えば、50歳で年収500万円の人が交通事故により後遺障害等級9級の後遺症を受けた場合の逸失利益は次のように計算します。
500万円(基礎収入)×0・35(9級の労働能力喪失率)×11・274(50歳の場合、67歳までの就労可能年数は17年で、その係数は11・274)=1972万9500円
「後遺症慰謝料」も裁判基準では目安が決まっており、9級の場合は640万円(平成10年基準、12年基準)とされています。
|
 |
 |
Q3 |
過失相殺
自動車を運転して、信号機のない交差点を直進中、左方道路を直進しようとしている自動車と衝突し、けがを負いました。相手方は私の側にも「過失」があると言って、損害賠償額の減額を求めてきますが、これは仕方がないことでしょうか。 |
 |
 |
A3 |
交通事故、殊に車両同士の衝突の場合、一方の運転手が全面的に悪く、他方の運転手に全く非がないというケースは少なく、多かれ少なかれ、いずれの運転手も落ち度が認められることが多いように思われます。
被害者であっても、損害の発生・拡大について落ち度が認められる場合にはその落ち度の割合により損害賠償額の減額がなされます。これを「過失相殺」といいますが、交通事故の場合、その基準がある程度、定型化されています。
一般的に用いられるのは、東京地裁の交通部(第27部)が過去の裁判例などをもとに作った「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」です。
本件のようなケース、すなわち同幅員での直進車同士の事故の場合、両者の速度が同程度であれば、その過失は左方車が4割、右方車が6割とされています。
したがって、このケースでは6割の過失相殺が適用され、損害額が大幅に減額されることになりかねません。 |
 |
 |
Q4 |
自賠責保険に対する直接請求
交通事故でけがをし、1週間通院することになったのですが、加害者の誠意がなく、休業損害や慰謝料等賠償金を払う素振りが見られません。自賠責保険会社に「直接請求」することはできるでしょうか。 |
 |
 |
A4 |
責任保険は本来、加害者が被害者に損害賠償を支払った場合に加害者側から請求することが原則です。しかし、加害者請求しかできないと、加害者に誠意がない場合には被害者が補償を受けられない事態になります。そこで、自賠法(16条)では被害者救済の観点から被害者の自賠責保険会社に対する直接請求を規定しました。
したがって自賠責保険会社に対して自賠責保険の請求をすることは可能です。
|
 |
|
| 改正民法の保証規制の概要 |
 |
 |
1, 従来は、会社の債務について、代表者等の個人が包括根保証をすることが金融実務では一般的であったため、企業の破綻の際には代表者等の個人が多額の保証債務の履行を求められ、破産に至る事態が常態化していました。
しかし、それは代表者等の個人にとって苛酷であると共に、このような制度が起業の促進を妨げ、廃業における障害になっているとの認識のもと、平成16年11月に民法が改正され、平成17年4月から新たな保証規制がなされるようになりました。
以下ではその概要について説明します。 |
2, 保証契約の様式行為化
保証契約は、従来は諾成契約とされ、特別の方式によることを要件とはされていませんでしたが、改正民法では「保証契約はすべて書面でしなければ効力を生じない」(民法446条2項)とされることになりました。これは書面作成を求めることにより、保証することを慎重にさせ、また外部的に明らかになっている場合に限って法的拘束力を認めるのが妥当と考えられたからです。
なお、この場合の書面には電磁的記録によるものを含むとされています。 |
3, 貸金等根保証契約にかかる特則
| (1) |
貸金等根保証契約と極度額規制~個人包括根保証の無効化
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証債務(根保証契約)であって、その債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債権(貸金等)が含まれるもののうち、保証人が法人であるものを除くものを「貸金等根保証契約」とし、かかる貸金等根保証の保証人が負う責任の範囲について、主たる債務の元本、利息・違約金・損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの、その保証債務について約定された違約金・損害賠償額について、その全部に係る極度額を限度とし(465条の2第1項)、その履行をする責任を負うとする「極度額規制」が設けられ、極度額を定めなければ無効になり(同第2項)、代表者等の個人包括根保証は許されなくなりました。 |
(2) |
元本確定期日の期間制限
貸金等根保証契約において、主たる債務の元本確定期日の定めがない場合には、当該保証契約締結日から3年を経過する日をもって元本確定期日をするとされました(465条の3第2項)。貸金等根保証契約で、元本確定期日を定めることは認められますが、当該保証契約締結の日から5年を経過するまでの範囲で定めなければならず、5年以降の確定期日を定めた場合には当該確定期日の定めが無効とされます。 |
(3) |
元本確定事由の法定
①保証債権者自身が主債務者または保証人の財産に対し強制執行や担保権実行を申し立てた時、②主債務者または保証人が破産手続開始決定を受けた時、③主債務者または保証人が死亡した時には当然に元本の確定を生じるとされています。 |
(4) |
経過措置
| ① |
保証の要式行為に関する経過措置
保証の要式行為についての規制は改正法施行前の保証には適用されません。 |
| ② |
極度額規制と改正法施行前に既存契約
極度額規制も施行前の貸金等根保証契約には適用されません。 |
| ③ |
元本確定期日規制に関する経過措置
改正法施行前に締結された極度額の定めのない契約であって、その元本確定期日がその定めにより改正法施行日から起算して3年を経過する日より後の期日が定められているものについては、施行日から起算して3年を経過する日をもって元本確定期日とします。また改正法施行前に締結された契約であっても元本確定期日の定めのない場合については、その契約に極度額の定めがあるか否かを問わず、改正法の施行日から起算して3年を経過する日をもって元本確定期日としています。 |
| ④ |
元本確定事由に関する経過措置
元本確定事由に関する改正法465条の4の規定は、既存の貸金等根保証契約に適用されます。また改正法施行前に改正法465条の4各号に掲げる場合に該当する事由が生じた契約であって、その主たる債務が確定していないものについては、施行日にその事由が生じたものとみなして上記規定を適用するものとされています。 |
|
|
|
|
 |
| 以上 |
| (参考文献)「(改訂増補版)保証契約の法律相談」(青林書院) |
 |
|
|
 |